ブログ
教育機関における様々なアカデミックハラスメント
大学・高等教育機関におけるハラスメントの特徴
 教員であるとはいえ、教員(=人)が集まるところ、どこにでもハラスメントの芽は潜んでいます。大学や高等教育機関の教員たちは、その分野でのスペシャリスト、高度の専門的知識を有し、その地位につくまでは、莫大な時間と労力、資金、気が遠くなるくらいの努力と工夫が注ぎ込まれています。そこから生まれた業績は教員のプライドであり、その人の生き様であるとも言えるでしょう。
教員であるとはいえ、教員(=人)が集まるところ、どこにでもハラスメントの芽は潜んでいます。大学や高等教育機関の教員たちは、その分野でのスペシャリスト、高度の専門的知識を有し、その地位につくまでは、莫大な時間と労力、資金、気が遠くなるくらいの努力と工夫が注ぎ込まれています。そこから生まれた業績は教員のプライドであり、その人の生き様であるとも言えるでしょう。
専門分野の中で生きてきた教員の多くは、とても個性的であり、そのコミュニケーションは限られた場とスタッフの中で行われることが多いです。
私も大学の現場のほんの一部で非常勤講師として授業を持っていますが、時々、先生方の個性の強さに圧倒されることがあります(あなたも相当な個性の強さがありますよ!あなたに言われたくない、と言われるかもしれませんが、、、)
また、多様な背景を持つ専門家の集まり、それが職場ですから、自分の考えに反対の人、自分にはっきりものを言う人、なんだか自分とウマが合わない、カチッと来る人、違う大学出身の人、そんな人と話す時は、誰でも多少のプレッシャーがかかるものです。このような小さなプレッシャーが積み上がっていくと、ハラスメントとして職場に大きな問題を投げかける恐れがあります。
様々な背景を持つ学生が集まる大学
 例えば、私が教える大学のクラスを眺めてみると、4分の1が留学生です。文化習慣、そして宗教まで異なる人たちです。日本人学生だって、家族の環境、小さい頃からの勉強の方法も千差万別、みんな違うのです。様々な背景を持つ学生に教室という現場で対応していくのが教員たちです。
例えば、私が教える大学のクラスを眺めてみると、4分の1が留学生です。文化習慣、そして宗教まで異なる人たちです。日本人学生だって、家族の環境、小さい頃からの勉強の方法も千差万別、みんな違うのです。様々な背景を持つ学生に教室という現場で対応していくのが教員たちです。
激動の今日の日本社会、ハラスメントに関わる考え方や施策もどんどん変わってきました。また、若い人たちのコンプライアンスの意識も高くなりました。教員たちは、自身の専門性を高めるための研究を続けると同時に、学生への指導や接し方も考えなくてはならない、また、自分自身もハラスメントだ、とあらぬ誤解を受けぬよう、ハラスメントに関わる知識を学ばなければならない、そんな大変な時代がやってきたのです。
私たちは「昭和」を引きずってはいないか 〜昔よくても今はダメ!なこと

ある大学の有名な教授、A先生の研究室では、毎年一定数の学生が大学に来なくなり(いわゆる不登校)ます。その中の数名の学生から相談を受けた健康管理センターからは「ブラック研究室」とレッテルを貼られてしまいました。
ある時、私が教えた学生の件で、A先生と話す機会がありました。研究室に行くと、先生は少年のように、熱心にそしてワクワクしながら、最近の研究について(私が分かってもわかっていなくても)語ってくれました。まさに好奇心いっぱいの少年が目の前にいるようでした。研究に対しては、どこまでも純粋なのです。
それからしばらくして、話は不登校になっている学生のことに及びました。先生は、ちょっと昔を振り返るような顔になって
「私は私の恩師から厳しく指導をされた。1年358日、お盆と正月だけ休み、あとはずっと研究室か大学にいた。昔はみんな苦しくても教授についていった。私が教授になった時、恩師から指導されたように学生を指導した。なぜか、学生が研究室に来なくなった。今の学生は弱すぎる」
「今の学生は弱すぎる」と言いながらも、A先生は薄々時代の激しい流れ、若い人たちの価値観の変化に気が付いてはいたようです。「自分は今の若い学生に対してどのように教えたらいいかよくわからない」というのが本音のようでした。
キャリアストラテジーの大学・高等教育機関の教員むけハラスメント防止研修
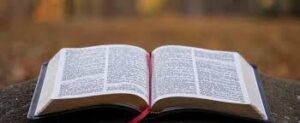 個性的な専門家にとっては「自分の指導方法がハラスメントに取られるのではないか」と、マイナスのイメージの強いハラスメント防止研修ですが、双方向参加型のアクティブラーニングを用いたワークで、自由に意見交換できる「明るいハラスメント防止研修」に変えていくと、ハラスメント防止は、受講者の心の中で、目に見える変化に向かって動き始めます。たとえ、それが大学の著名な教授であってでも、です。
個性的な専門家にとっては「自分の指導方法がハラスメントに取られるのではないか」と、マイナスのイメージの強いハラスメント防止研修ですが、双方向参加型のアクティブラーニングを用いたワークで、自由に意見交換できる「明るいハラスメント防止研修」に変えていくと、ハラスメント防止は、受講者の心の中で、目に見える変化に向かって動き始めます。たとえ、それが大学の著名な教授であってでも、です。
キャスト(キャリア・ストラテジー)の講師は大学や教育機関での現場の教員経験があり、高度な専門的技術を持つ教員向けのハラスメント防止研修の経験も豊富、対応も柔軟です。大学は企業や官公庁とはまた違った組織風土であり、アカデミックな教育現場です。キャストでは、大学や高等教育機関での教育経験を活かし、専門家の教員たちへのコミュニケーション&ハラスメント防止研修を進めています。
また、別途、個人対応の「ハラスメント行為者更生(行動変容)プログラム」「セクシャルハラスメント行為者対応プログラム」「サーバントリーダーシップ研修」も準備されております。
アカデミックハラスメント防止研修の詳細、ご質問等はHP「お問い合わせ」からどうぞ!
