ブログ
ハラスメントで通報されるかも〜部下を注意できなくなった管理職
部下を注意できなくなった管理職
 こんな事例があります。
こんな事例があります。
「徳川主任は部下Aを呼んで、仕事上のミスについて指導しました。部下Aは、徳川主任の指摘について否定。自分の意見を主張しました。徳川主任はもう一度指導しましたが、Aはさらに強硬に自分の意見を主張したので、このままではハラスメントで通報されると思い、それ以上の指導をしませんでした」
昨今、コンプライアンスの意識が高まり、部下にハラスメントで通報されるのを恐れて、指導することに躊躇を覚える管理職が多くなりました。
事例の徳川主任の気持ちは、わからないでもないですが、、、でも、ここで確認しておきたいことがあります。
「厳しい指導=ハラスメント」「厳しい指導≠ハラスメント」
私たちは「厳しい指導=ハラスメントか」と心配しがちですが、あるポイントをしっかりと押さえていれば、「厳しい指導はハラスメントではない」ということになります。つまり「ハラスメントはハラスメント」、「厳しい指導は厳しい指導」決して同じではない、ということです。それではその違いは何でしょうか?
![]()
確認してみましょう。
その指導はハラスメント? 「はい」あるいは「いいえ」で考えてください。
□侮辱・暴言等、人格否定等、精神的な攻撃を加えていないか
□何度も同じことを執拗に繰り返していないか
□指導の時間が長すぎないか
□遂行不可能な業務を与えていないか
本人ができるかどうか、過大な期待をせず、冷静に事実を確認
□個人のプライバシーを侵害していないか
□本来の仕事を取り上げていないか
□仲間はずれ、無視等個人を疎外していないか
上記に当てはまらない場合は、言い方伝え方の問題は別として、「ハラスメントではない!」ということになります。

誰でもがハラスメントで訴えられる?!
実は日本にある「〇〇ハラスメント(パワハラ、セクハラ、マタハラ、カスハラ、、、etc)」の数ですが、なんといくらでも作れるので、現在300ほどあるのではないか、と言われています。こうなると「ハラスメントハラスメント(=なんでもがハラスメントだと訴える)」を考えても、私たちはいつでも若い人も歳をとった人も、誰もがハラスメントで訴えられる恐れがあります。
ですから、ハラスメントとは何か、ということを、自分自身を守るために、みんなが認識する必要があります。
もう一度、その指導はハラスメント?の基準を考え、押さえておきましょう。
□侮辱・暴言等、人格否定等、精神的な攻撃を加えていない
□何度も同じことを執拗に繰り返していない
□指導の時間が長すぎない
□遂行不可能な業務を与えていない
本人ができるかどうか、過大な期待をせず、冷静に事実を確認
□個人のプライバシーを侵害していない
□本来の仕事を取り上げていない
□仲間はずれ、無視等個人を疎外していない
きっちり自分の意見を主張する若い人たち

上司や目上の人たちに、自分の意見を明確に主張したり、反論したりする、、昭和に生まれ育った人には、ちょっと驚きかもしれません。この背景には、社会的な価値観の変化があります。たとえば、下記はいかがでしょうか?
1)ハラスメントの概念の浸透や、年功序列型の雇用システムの崩壊
2)コンプライアンス意識の浸透
3)教育の変化 自分の意見を明確に主張
4)立場や年齢に関係なく、言うべきことは言って良いという風潮
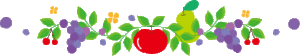
別の視点から考えてみましょう!
目の前にいる社員は社員であると共に「発達段階では青年期」
我が家の次男はかなり長い反抗期がありました。親の言うことにいちいち反対、大学を中退、好きな音楽をやり、家出(短期)、引きこもり等を経て、やっと資格を取り大型バスの運転手として就職しました。親はこんなことに直面すると「うちの子どもは特別だろうか」と思うのですが、、実は発達段階では、ほぼほぼ一般的、ということになります。(と、今は言えますが、当時はかなり悩みました)
エリクソンという学者は、人間の一生を8つの心理社会的段階に分け、それぞれの段階で乗り越えるべき「課題(心理社会的葛藤)」があると述べています。
その中から「青年期」「成人前期」(18歳〜30歳)に焦点を当ててみると、
① アイデンティティ(自我)の確立
自分が「何者か」を模索し、価値観や人生観を形成する、進路選択(大学・就職)を通じて、将来について考える、「自分らしさ」を追求し、社会の中での役割を意識する
② 感情の起伏が激しい
自立心と依存心の間で葛藤する(親との距離感)、承認欲求が強まり、周囲の評価を気にする、失敗や挫折への耐性がまだ未熟で、落ち込みやすい
③ 批判的思考の発達
社会問題や道徳的価値観について自分なりの意見を持つ、大人の意見に反発しやすく、「正義感」が強まる、「なぜ?」を考える力が育ち、自分の考えを主張するようになる
この3つの特徴があるかもしれません。
私たちは、目の前の社員をみると、自社の社員ではあるから「〜のようにしてほしい、〜すべきだ」と思うのですが、一方で、相手は「揺れ動く、繊細で、自分探しをまだまだしている青年期」となります。
それじゃ、どうするか!?
 ハラスメントが生まれにくい職場環境はどのようなものでしょうか?基本的には「コミュニケーション」が円滑な職場はハラスメントが起きにくい、と言われています。
ハラスメントが生まれにくい職場環境はどのようなものでしょうか?基本的には「コミュニケーション」が円滑な職場はハラスメントが起きにくい、と言われています。
それでは「コミュニケーション」とはなんでしょうか?
この答えを求めると100人が100通りの答えを出してきます。「コミュニケーション」とは大きな大きな概念なのですが、、、。
実は大学等で学習する、オーソドックスな「コミュニケーション」は下記となります。
1)言葉を使ったコミュニケーション
①誰にでもわかりやすく伝える能力
②人の話を最後まで自分の意見を挟まなずに「聴く」能力
2)言葉を使わないコミュニケーション
①表情や身振り手振り等で相手に自分の気持ちを伝える能力
②相手の表情を読み取る能力
このコミュニケーション能力を身につけることで、または能力を向上させることで、職場のコミュニケーションを円滑にすることができるように思います。
![]()
例えば、
1)-① 誰にでもわかりやすく伝える能力について、考えてみましょう。
□難しい言葉を使わずに具体的に、相手に説明できているでしょうか?
□相手が理解しているかどうか、相手のの表情を読み取り対応しているでしょうか?
□質問しやすい環境を作っているでしょうか?
1)-② 人の話を最後まで聴く「傾聴力」
□仕事をしながら、相手の話を聞いていないだろうか。
□話を途中でさえぎり、自分の意見や「うんちく」を述べていないだろうか。
□大きく頷いたり、あいづちを入れたり、相手の話を引き出す努力をしているだろうか?
さあ、こんなたわいもないこと、これがとても難しいのもみなさん、もう十分ご存じだと思います。ハラスメント防止は、ハラスメントの概念が徐々に少しずつ浸透してきたのと同じように、少しずつ忍耐深く前に進ませていかなければならないと思います。
業務指導に自己主張をする社員への、対策は上記のようなことを積み重ねていくことから始まると思います。長い長い道のりです。
ハラスメント防止の意識は徐々に浸透してきた、、だから
 徐々にハラスメントを防止する具体的な方策を立てていかなくてはなりません。弁護士さんや社労士さんのお話と同時に、どのように具体的な方策を立てるのか、概論的ではなく、実際に時間はかかるけれど、効果のある方法を考える必要があります。
徐々にハラスメントを防止する具体的な方策を立てていかなくてはなりません。弁護士さんや社労士さんのお話と同時に、どのように具体的な方策を立てるのか、概論的ではなく、実際に時間はかかるけれど、効果のある方法を考える必要があります。
部下を業務指導することに躊躇を覚えてしまう管理職に対応する、コミュニケーション能力向上研修も効果があるように思われます。
ただ、対応する職場によって、職場の風土が異なります。職場の症状に合わせた繊細な「ハラスメント防止研修」「ハラスメント予防研修」が必要だと思います。
 吉本惠子 株式会社キャリア・ストラテジー代表 ハラスメント防止、ハラスメント予防、ハラスメント行為者行動変容プログラム、コミュニケーション能力向上研修等「人が生き生きと働くことのできる職場作りの支援」を行っている。都内の大学、大学院で非常勤講師を務める。大学等での専門は言語・多文化共生(多文化協働)
吉本惠子 株式会社キャリア・ストラテジー代表 ハラスメント防止、ハラスメント予防、ハラスメント行為者行動変容プログラム、コミュニケーション能力向上研修等「人が生き生きと働くことのできる職場作りの支援」を行っている。都内の大学、大学院で非常勤講師を務める。大学等での専門は言語・多文化共生(多文化協働)
